top of page
にいはま


【白鵬・その9】富樫宣資(無門会空手宗主)
『白鵬の情熱を満足させるものは「後の先」だけだった。』とは朝田氏の評。 その「後の先」は我が無門会空手の「受即攻」でもある。 無門会空手の宗主、富樫会長の弟子とのちょっとした対談(2019.1.31)に極意の片鱗をみる。前田4段との「大坂なおみの試合から受即攻まで(仮称)」...
khiro1
2023年6月16日読了時間: 3分
閲覧数:20回
0件のコメント
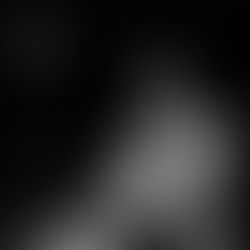

【白鵬・その8】囚われない
流れ、無意識や心、拍子について。 大横綱と、「五輪書(風の巻)」の津本陽(作家)の解釈。。 大切なのは流れ(双葉山)(白鵬) 双葉山が横綱だったころ、横綱は4人いたが全員が千秋楽までいったのは昭和13年の夏場所のみ。双葉山は3横綱に全勝。その決まり手がすべて違ったことを記者...
khiro1
2023年6月16日読了時間: 2分
閲覧数:13回
0件のコメント


【白鵬・その7】日馬富士との一番
2010年秋場所は、双葉山の「69」を目指しての48~62連勝の一番脂がのっていたとき。白鵬曰く、「後の先」が完璧に決まったという一番を振り返る。 千秋楽の日馬富士戦(大関) 日馬富士の立ち合いは完璧に思えたが次の瞬間、白鵬は何事もなかったかのように、日馬富士の体を軽々と押...
khiro1
2023年6月16日読了時間: 2分
閲覧数:6回
0件のコメント


【白鵬・その6】後の先
後の先(ごのせん) 無門会空手の人はお気づきだろう。「後の先」は『受即攻』に置き換えることができる。そうするとグッっと臨場感が増す(笑) 白鵬の「後の先」の取組みを紹介。 2009春場所4回 。北勝力、稀勢の里、日馬富士、朝青龍...
khiro1
2023年6月16日読了時間: 3分
閲覧数:9回
0件のコメント


【白鵬・その4】千代の富士
あこがれの千代の富士 「若いころ千代の富士のビデオをよく見てまして…」 白鵬の守破離(しゅ・は・り)の守は千代の富士の模倣だった。 千代の富士の『左前みつを取って一気に走る』相撲。右指し、左上手からの切れ味鋭い上手投げはその後、白鵬スペシャルと言われる。...
khiro1
2023年6月16日読了時間: 2分
閲覧数:5回
0件のコメント


居つきとは何か?(合気13)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その13) 「居つく」は一般的には足がその場に止まってしまって動けない状態をさす。 昔の日本人は連続して動いていたものが、そこにとどまることを「居(ゐ)る」と言った。 ちょっと立ち寄って立ち飲みする「酒屋」に対して座敷のある「居酒...
khiro1
2023年6月12日読了時間: 2分
閲覧数:53回
0件のコメント


極限の突き、蹴り(合気12)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その11) 示現流の必殺の剣は、胴体ごと斬る勢いでの極限の太刀使いだった。 先述の「山田編集長のアマチュア中国武術チームが本場ムエタイで善戦」の勝因は攻脈線を取ること、そして極限の突きの2つにあったと考える。...
khiro1
2023年6月12日読了時間: 2分
閲覧数:22回
0件のコメント


必殺の剣、その秘密(合気11)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その11) 武術の技術体系の中に、出力練習を目指した稽古をよく見かける。一例が薩摩の示現流(じげんりゅう)。幕末の動乱期や西南戦争などで、実際の斬り合いで驚くべき殺傷力を示したことで知られる。その理由もよくわかる。...
khiro1
2023年6月12日読了時間: 2分
閲覧数:13回
0件のコメント


多人数・武器アリの稽古とは?(合気08)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その8) 合気道(ほか伝統武術)はなぜ弱いのか? で考えた要訣の2つめが「対抗性運動の消失」だ。組手がない、試合がない。 格闘技の優れた点は、練習や試合の対抗性運動の中で技を習得していけることだ。かたや伝統武術にはそれが無い。そも...
khiro1
2023年6月12日読了時間: 2分
閲覧数:7回
0件のコメント


攻脈線が生きる無門会空手(合気07)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その7) 武術考キーワードの一つ、「攻脈線」が生きる空手が無門会空手だ。無門会の高段者の戦いは図の間合いにて、お互いの顔面を狙いあう静かな戦いとなる。 単純攻撃、それをカウンター、そのカウンター意識の間隙を破る攻撃、その意識をさら...
khiro1
2023年6月12日読了時間: 2分
閲覧数:10回
0件のコメント


ムエタイに負ける空手!?(合気05)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その5) ムエタイはなぜ立ち技最強と呼ばれるか? エネルギー投射の効率論と確率論から考察した。 戦争では、爆弾などを相手の陣地にいかに効率的に、確率高くして打ち込めるか、すなわち相手にエネルギー投射できるかで勝敗は決まる。...
khiro1
2023年6月12日読了時間: 2分
閲覧数:36回
0件のコメント


【白鵬・その3】稽古
ウォーミングアップのあと、ぶつかり稽古への流れ。 四股 太ももの裏側、臀部、腹筋、そして足裏の筋肉まで増強する。古の力人の英知が詰まった稽古法。大鵬は若手時代に毎日500回ふんだ。大東流合気柔術の達人、佐川師範は仕事で海外出張する弟子に『四股だけでいい。ただし毎日千回』を課...
khiro1
2023年6月7日読了時間: 3分
閲覧数:7回
0件のコメント


【白鵬・その2】少年時代
1985年生まれ、5人兄弟の末っ子。上の3人はお姉さん、2000年に日本に来るまで両親と川の字で寝てたという箱入り娘ならぬ息子だった。 父はモンゴル相撲の横綱、そしてレスリングでオリンピックのモンゴル初メダリストとなり英雄、母は医者で裕福な家庭で育つ。14、15才頃から日本...
khiro1
2023年6月7日読了時間: 2分
閲覧数:3回
0件のコメント


【白鵬、その1】禅問答
優勝回数、大鵬の32を超え45。通算勝ち星1187でトップ、双葉山の連勝69には届かずも63。大横綱「白鵬」について、その1。 ある敗け試合の後のコメント「弱すぎたから負けた」を、インタビューアーはそのまま受け取ったが、後に白鵬は彼を訂正。「主語が違う、むこうの力士」と。...
khiro1
2023年6月7日読了時間: 2分
閲覧数:11回
0件のコメント


宮本武蔵は集団戦を勝ち抜いた(合気04)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その4) 日本でも中国でも武芸十八般と言われ、様々な武器術を学ぶことが戦国時代の習わしであったが、その技を完全に習得は無理で、あくまで武芸全体の体系を表す言葉だったと思われる。...
khiro1
2023年6月6日読了時間: 3分
閲覧数:10回
0件のコメント


古武術とはなにか。そもそも論(合気03)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その3) 古武術とはなにか。 古武術とは明治以前の武術でそれを習得、使用を許されたのは武家のみだった。その目的は主君をガードするため。 ヨーロッパの騎士は王を守るガードマンである以前に他国を襲う侵略者(キング同士の戦い)で、そのや...
khiro1
2023年6月6日読了時間: 3分
閲覧数:7回
0件のコメント


グレコローマンスタイル、誕生秘話(合気02)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その2) 武術の原始形態は武器も含めた総合武術である。実際の戦闘模様はあまりに多様だがその複雑なものを単純化、細分化して訓練するのが効果的だ。そんな合理的な軍事訓練を競ったのが古代オリンピックだ。...
khiro1
2023年6月5日読了時間: 3分
閲覧数:11回
0件のコメント


バーリトゥードは実戦的で無い!?(合気01)
「合気道はなぜ強いのか?」から考える武術論(その1) 格闘技の一番の大会は?の問いに「UFC」と答える人が多い。バーリトゥードという真剣勝負の総合格闘技だ。ところで急所攻撃の禁止ほか幾つものルールで縛られる。 視聴者ありきの興行がベースだからどうしてもそうなってしまうし、過...
khiro1
2023年6月5日読了時間: 2分
閲覧数:13回
0件のコメント
bottom of page